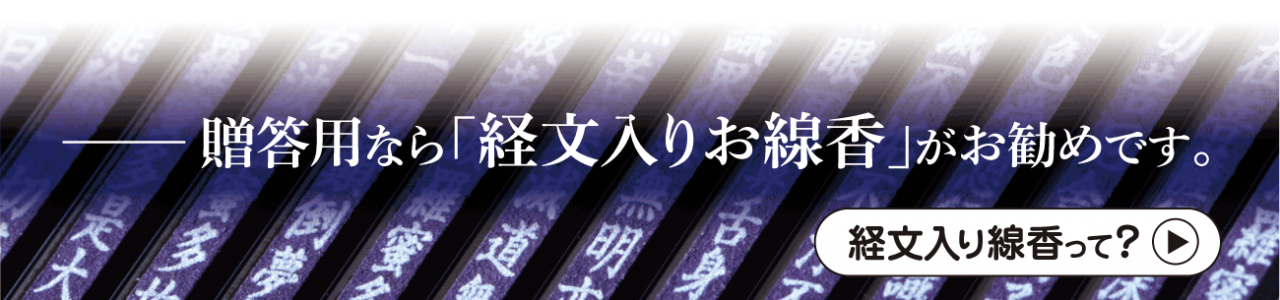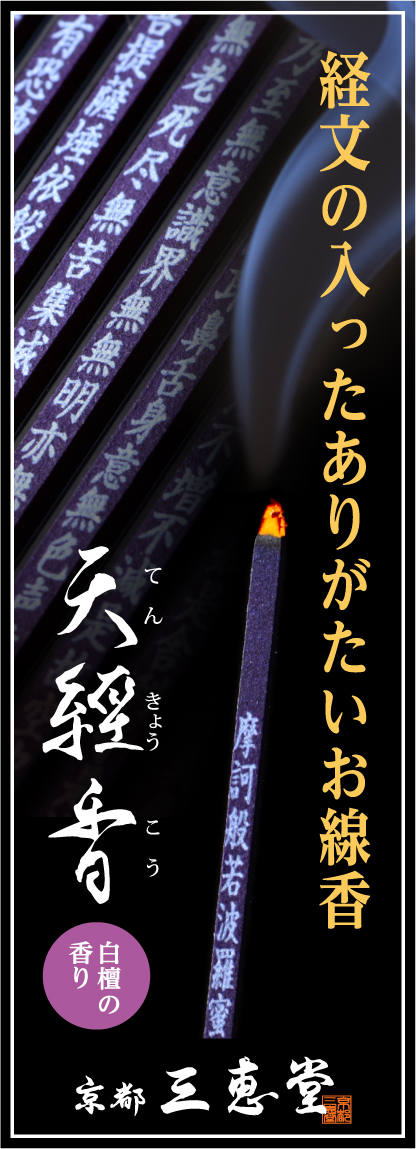お悔やみを伝えたい.com
2018.09.28
大学時代の恩師の四十九日。連名でお供えをしたいが気をつけることは? (25才男性 会社員)

まず、「連名が失礼にならないか」についてお答えします。結論、まったく問題ありません。むしろ連名にすべきです。ゼミのOBであれば、ご遺族が皆さんのことをご存知ないことの方が多いでしょう。知らない方から続々とお供え物が届く…。皆さんの厚意がかえってご迷惑にならないとも限りません。
1. 予算
個人でお供えをする場合の相場は3,000~5,000円といわれています。これを目安に「相場×人数」と「相場÷人数」という2つの考え方があります。それぞれ一長一短です。
「相場×人数」の場合、人数が多くなると総額がどんどん高くなり、先方が恐縮されてしまうことがあります。一方、「相場÷人数」の場合、2~3人ならともかく、4人以上だと一人当たり1,000円前後となり、いい大人が送るにしてはいかがなものかと。
こういったことに正解はありませんが、今回のケースであれば総額5,000~10,000円が妥当かつ先方の心のご負担にならない範囲ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
2. 品物の選択
さて、予算が決まったところで品物選びです。一般的には①食べもの ②供花 ③お線香・ロウソクなどに分けられます。
①食べもの
おまんじゅうなどのお菓子や果物が一般的です。故人が好きだったものをお供えするのもよいでしょう。なお、食べものの場合は「日持ちするもの」「小分けできるもの」が望ましいでしょう。
②供花
花は白が基本です。もし色を混ぜるなら、紫か青くらいまでとされています。ですが、故人が好きだった花を送るときは、白や青でなくても良いでしょう。
③お線香・ロウソクなど
食べものには賞味期限があり、花には水やりなどの手間がかかります。そういった意味では、お線香やロウソクは場所もとらないので無難なお供え物といえるでしょう。またお線香には、お清めの意味があり、さらに線香の煙が成仏した故人のお食事代わりになる、線香から立ち上る煙が極楽浄土への道のりになるともいわれています。
なお、仮に予算を10,000円とするなら、食べ物の場合、どうしても量が多くなってしまいます。そこで「食べものにお線香orロウソクを添える」とするのもよいでしょう。
3. 表書き
「御霊前」それとも「御仏前」?
四十九日までは故人は「霊」の状態で、四十九日法要で成仏し、「仏」になると考えられています。そのため、四十九日法要では「御仏前」を使います。もし、迷われたなら「御供」がもっとも無難といえるでしょう。また、西日本では「粗供養」もよく使われています。
送り主の名前
次に水引の下に書く送り主の名前について。連名の場合は、3名までは氏名を連記してOKです。4名以上の場合は、代表者の氏名を中央に書き「他一同」とするか、「〇〇大学△△ゼミ」+「代表者氏名」+「他一同」、あるいは「〇〇大学△△ゼミ一同」とします。個々の氏名は便せんなど別紙を用意して記します。できれば後述する手紙を添えるのがベストです。
参考までに、名前を連ねる場合の順番は「右が格上」と覚えておきましょう。友人同士など同格の場合は五十音順に右から並べます。
文字の色
文字の色は薄墨ではなく、濃墨(黒)で書きます。通夜と葬儀は薄墨で、それより後の法要では濃墨が一般的とされています。葬儀や通夜は突然の訃報で墨をする準備もままならないから、というのが謂われです。
.
4. 手紙を添える
お供えを送付する場合、品物だけを送るのは事務的で冷たい印象を与えてしまいます。また、ご遺族が皆さんのことをご存じない場合、その間柄を書かないと、対応に苦慮されることもあります。お悔やみの手紙を添えることは受け取る側の気持ちの慰めにもなりますので、ぜひ用意しましょう。また表書きで「他一同」とした場合は、手紙末尾の差出人の欄に全員の氏名を記すとよいでしょう。
手紙には、まず故人と自分たちの関係を書き、お悔やみの言葉と葬儀に参列できなかった非礼を詫びます。さらに故人の人となりやエピソードを添えるとご遺族にとって慰めとなるでしょう。また、マナーとしては、重ね重ね、ますます、いよいよ、次々などの重ね言葉に気をつけましょう。